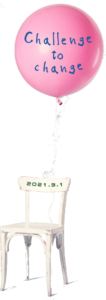近い、って気付いたのは多分だけど俺が先だったと思う。隣に座ってたあのコがほら見てよ、ってスマホの画面を向けるから何も考えずに覗き込んだらちょっと皆には言えないけど面白い画像見せられて、油断してたから思わず噴き出しちゃってソレにつられて向こうもお腹抱えて笑い始めてさ、今思い出したら別にそこまで面白いわけじゃないんだけどそのときはツボっちゃって他にも見せてよなんて肩寄せて、そしたらいつもよりずっと顔が近くて笑ってる横顔がすごくかわいくて見てたら向こうも気付いて固まって視線が重なって何か静かになっちゃって、わかるでしょ? ちょっとイイ感じだったから……。でも起ころうとしたことにビックリしたみたいで飛び退かれちゃって、あ、やべ、と思って取り繕うとしたんだけど「用事思い出したから帰る」ってすぐ行っちゃってさ、それから何となく? 気のせいかもしれないけど? もしかしたら? 避けられてるのかな~って思ってるんだよね。
「それが俺の隣の席のヤツのことなら、まあ間違いなくここんとこお前を避けてるな」
何を隠そう、目下の俺の想い人、隣のクラスのみょうじなまえのことだ。
そう高らかに宣言すれば、とうの昔に知っていたとばかりに溜息を寄越された。岩ちゃんなんて、部室の隅でいじけていた俺を引っ張り出して、珍しくも理由を訊いてくれるものだから話したのに、今はまるで毛虫でも見るような顔を俺に向けている。ぐるり部室を見回すと、まっつんもマッキーもそう変わりはなかった。
「つまり、イケると思ったら失敗しました、ってこと?」
「サイテーだな」
「やだ及川クン、野蛮〜」
三者三様の心無い言葉は俺の頭上に重石としてのし掛かった。ずぶずぶと地中にめり込んでいく気持ち。追い討ちをかけるように岩ちゃんが「本人の了承得ずに手ェ出すとかアリエネーだろ」なんて高尚なコト宣う。
「それはそうだけど雰囲気ってものがあるじゃん? え、まさか岩ちゃん。手を繋ぐのもキスもそれ以上も毎回そのウブでクソ真面目なカンジで『……いいか?』とか聞いてるわけじゃないよね? うわ~、カノジョ大変そう……」
緊張で眉を吊り上げた顔をつくった岩ちゃんのモノマネは思いのほか上手くできて、マッキーには大ウケしたようだ。まっつんも噴き出しながら「言ってそう」と震えている。
でしょー、俺ってば観察力ある。伊達に幼馴染みやってないよね。
得意になって鼻の下をこすったところで、派手なげんこつを食らった。
◇
牛乳パンを頬張りながら改めて朝練終わりと同じ議題に思考を巡らせる。言ってみろと言うから相談したのに、誰も彼も薄情なもんだ。とはいえ、あのコのことで部員たちに悩みとも言えない悩みを打ち明けるのは別に初めてのことじゃない。朝練から教室へ向かう道すがらが一緒だったからと一喜一憂したり、同クラ特権で岩ちゃんが貰った調理実習のマフィンを奪い取ったり、これまでそこそこ忙しなく恋の話題を提供してきた。だからこそ「またか」って態度になるんだろうけけど。
それでも今は、これまでになかったとんでもない一大事なんだよ。
チャンスだと思ってがっついたことは、認めよう。据え膳、とまではいかないけど、今がそのタイミングだって思ったんだから仕方ない。少しずつ関係性を築いてきて、正直脈ありだと思ってたからこそのチャレンジだ。まあ、時には失敗もある。視野に入れなかったわけじゃない。
だからって、ハイこれでおしまい諦めましょう、というわけにはいかない。打開策を考えて次の一手だ。
何がいけなかったんだろう。もしかしなくてもファーストキスまだとか? でも去年カレシ居たと思うんだけど。いや、でももしそうだったとしたら、俺サイテー? ファーストキスなのにあんな面白画像見てバカ笑いしてムードも何もあったもんじゃないときにキスしようとしたの? うわ、それはヒドイ。他人ごとみたいに考えてみると少し反省できた。
……嫌われたかもしれない。だったら、一時退却も作戦のひとつかだろうか。気まずいまま、何となく時間が解決するのを待って、いつかなあなあに誤魔化せる日が来るのを待つか。気持ちも伝えてないのに? それはないデショ。
目的の教室を覗くと「よぉ及川、また岩泉か?」とは廊下側に座る男子から。そうだね、いつもの俺ならそうなんだけど、今日の目的はそうじゃない。教室を見回すと、すぐに目的の人物としっかり目があった。
知ってる。俺って目立つから、違う教室に入ったら皆一度は視線をくれるんだよね。無意識だって分かってるよ。だからさ、そんなあからさまに目を逸らさなくてもよくない?
ずかずかと教室に入って行って、その机に両手を降ろした。
「話あるんだけど」
思ったよりも両手が大きな音を立てて、華奢な肩を跳ねさせてしまった。視線を送った顔はみるみる間に青褪めて、えっそんなに拒否ることある? と少し焦って岩ちゃんに助けを求めてしまう。もう一方からも同じように助けを求める視線を送られたらしい岩ちゃんは、眉間の皺を深くしてそれはそれは大きな溜息を吐いた。
「どっかヨソでやれ」
双方の首ねっこ掴んで廊下へ放り出された俺たちは座り込んで顔を見合わせる。行き交う生徒たちからまたやってる、と苦笑を送られた。
「……とりあえず、場所変えよっか」
目の前の彼女に見慣れた明るい表情はなく、眉毛は情けなく垂れ下がっている。それでも頷いてくれたことに安堵した。先に立ち上がり手を差し伸べる。素直に手を取ってくれたことに安堵した。それを離さないままに廊下を進む。
「ちょ……、及川」
「いいからこっち」
明らかな戸惑いが背後から伝わるけど、制止は聞いてやれない。冷やかすような誰かとすれ違うこともなく階段を下りて校舎を離れて、その先へ。コンパスの差のせいで後ろで時々足がもつれかけているのが分かっても、お構いなしに突き進んだ。
「ねぇ、どこ行くの」
「ここ」
指し示した先は部室棟。トーゼン向かうはバレー部の部室だ。先に彼女を招き入れてドアを閉める。特別散らかってはいないけど片付いてもいない。転がっているボールを拾い上げて適当なラックに押し込めた。彼女はきょろきょろと落ち着かない様子で部室を見回していた。中に入ってくれたはいいけどそこから動こうとはしない。
まあ、アウェイだよね。
「初めて入ったけど、ウチと全然違うね」
「運動部でも女子と男子じゃ違うだろうね。男バレはマネジもいないし」
キレイに使っている方だと思うけど、それでも女子と比べたら差は歴然だろう。その違いはどこで生まれるんだろうね。
所在なさげに突っ立って、それでも興味深そうにへこんだロッカーやまた落ちて転がったボールに視線を移していく彼女を観察した。やがて見られていることに気が付いて顔を赤くした彼女と目があって、だけどすぐに逸らされた。ここのところずっとこれだから、フツーに傷付く。
はあ、と溜息を吐き出したらビクついて、扉の外の通路を誰かが通ればまた飛び上がって、まったく見てられなかった。
「鍵持ってるの俺と岩ちゃんだけだから、鍵閉めちゃえば誰も入れないよ」
扉を背にして動こうとしない彼女越しに手を伸ばしてサムターンを回す。触れるようで触れない距離まで近づいたのは、わざとだ。すぐに離れて肩をすくめても彼女の緊張が解けることはない。
勢いでここまで連れてきたはいいけど、この先を考えていたわけじゃない。何から話そうか。あのときその唇に触れようとした理由? 初めて意識した日のこと? 会った日のこと? さすがにそれは覚えてない。一年の一学期なんて、正直認識すらしてなかった。だけど三年になってクラスが離れたことにショック受けて岩ちゃんに八つ当たりなんかして怒られて、そのくせ岩ちゃん理由に教室訪ねて話しかけたりちょっかいかけたりしちゃうんだから、俺って結構分かりやすいと思う。わかんないかな。わかってよ。わかんないなら訊いてよ。
「好きって言ったらどうする?」
ほんの出来心で勢いでそう口にした。やっぱり雰囲気もクソもなくて、しかも意地の悪い聞き方だと自分でも思う。すると彼女は、思いっきり顔を顰めて言った。
「言われないと、わかんない」
驚いて瞬きを繰り返す。それから肩の力を抜いて笑った。
そうだね。言ってないし、言われてもない。でもそんな顔してたら、言ってるようなもんだって分かってるんだろうか。どうやら嫌われてはいなかったようだ、と確信する。それから、脈ありっていうのも間違いじゃなかった。
「ねえ」
「……なに」
「好き。好きだよ」
ストレートに想いを告げればそれは想定しなかったのか、ボンッ、と音が聴こえるくらい勢いよく染め上がった。自覚はあるのか腕で顔を覆ってしまったけれど、覗く耳まで赤い。かわいい。
「ねぇ、こっち向いてよ」
「やだ」
「おねがい」
「やだってば、ばか、触んないで」
「あのさ、俺だって傷付くんだよ?」
「え、そうなの」
「俺のこと何だと思ってるの」
イケメンナルシストとかそんなところだろうなと思いつつ返事を待っていたら「考えすぎのバレー馬鹿」って返ってきた。なんだ。俺のことわかってるじゃん。
「俺をこんなにヘコませたり喜ばせたり悩ませたりするのはバレーの他に一人だけだよ」
もちろん今言った「バレー」の中には岩ちゃんを筆頭にバレー部の面々が連なってるんだけど、それは今わざわざ口にすることじゃないよね?
顔を覗き込まれないようにか、遂にはその場に座り込んでしまった彼女の前に腰を落とす。
「ちょ……顔ちかい」
「知ってる。でももっと近付きたい」
「なッ」
「うん」
「何も言ってない!」
「でも、ダメって言わないでしょ?」
こんなの全然スマートじゃないし、無理強いしたいわけじゃないんだけど、仕方ないよね。だって、みょうじがかわいいから悪い。
イヤなことはイヤだと言えないコじゃないって知ってる。気持ちを自覚した日のことも、あの日のことも、今触れたい理由も、みょうじが知りたいことは言葉にして伝えるよ。要らないって言われても言っちゃうけど。全部、好きだからだ。
だからお願い、嫌いじゃないなら触れさせて。