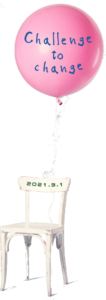
高校二年、進路に悩んでいた。走り出して大声で叫びたい気分だったけどまだ半分通う高校で変人認定されたくはないから、ぐっと我慢。制服のまま汗をかきたくもないから走るのも我慢。だけど結局落ち着かなくて、校内をぐるぐると歩き回った。じっとしているより少しでも身体を動かした方がいい。
普段はうろつかないところまで歩いてくると何やら荒らげた声が聞こえた。体育館だ。開け放されていた扉から中を覗けば、バレーボール用のネットがかかっていて、ここがバレー部の練習場所であることを思い出した。声の発生源はどうやら同学年の双子たちらしい。胸ぐら掴んで睨み合っているものだからぎょっとしたけど長引く話ではなかったのか、二人はすぐに離れてしまった。ならば速やかに離れるべきだったのに、うっかり体育館を見回したものだからそこに居た角名くんと目が合ってしまった。慌てて頭を引っ込めようとするも遅く、ひらひらと手を振られる。気付かないふりをして扉の陰に隠れてみたのに、わざわざ近付いてきてくれたらしい。面白いものでも見つけたかのような角名くんの声が頭上から降ってきた。
「何してんのみょうじ」
「……野次馬」
「ふっ、正直すぎ」
とはいうものの部外者が不躾に詳細を尋ねるのは気が引けて、「おっきい声聞こえたら気になるやん」とだけ言い訳をした。「てっきり練習見にきたのかと思った」と言うから、入部希望者でもないのにそんなもの見てどうするのか、と首を傾げれば「試合じゃなくても見に来る女子多いんだよ。誰かを目当てにして」と返ってきた。なるほどそういうことか、と再び体育館を覗き込む。全体での練習は行っておらず、自主練習時間のようだ。双子をはじめ各々単体でストレッチをしていたり、ボールと戯れたりしていた。見学に来る女子とやらも、なるほど別の扉からちらほらと覗いていた。
「あの二人、いつもあんな感じなん?」
「酷いときは取っ組み合いしてるよ。今日のは大丈夫なやつ。じいさんになったときの幸せ度で競うんだってさ」
「ふぅん?」
何の話かさっぱり分かりません、を顔に出しても、角名くんは説明してくれず笑うばかりだった。
『80歳なった時、俺より幸せやって自信持って言えたんなら、そん時もっかい俺をバカにせえや』
聞こえてしまった声を反芻する。じいさんになったとき、と聞いてヨボヨボの双子を想像しようとしたけど、うまく出来なかった。角名くんは飄々としてるところは変わらなさそう。誰にしてもバレー部の面々は背が高いから迫力あるおじいちゃんになるだろうな、と思った。そこまで考えて、誰の腰が曲がる想像も出来ないことに気が付いた。私はどうだろう。しゃんとしたおばあちゃんになれるだろうか。
双子の片方がバレーをやめるらしい、というのは後から人に聞いて知ったことだ。どうやらあの日の諍いはそれが理由だったらしい。侑くんはバレーを続けるけど、治くんは高校でやめて別の道へ進む決意をしていること。それをバレーからの「逃げ」みたいに言われて怒ったこと、治くんには譲れない想いがあってぶつかったということ。バレー部のファンであるクラスメイトが教えてくれた。
「でも治くんバレーめっちゃ上手いのに、もったいない!」
休み時間の教室、席が離れているとはいえ本人が教室にいる状況でのそんな発言。彼女に悪気はないんだろう。聞こえてはいまいか、と後方の席を見遣れば、治くんは机に突っ伏して寝ているようだった。胸を撫で下ろして正面に座る彼女へと向き直る。
もったいない、なんて。きっと聞き飽きるほど言われてるんだろう。彼はその言葉をどう受け取っているんだろうか。称賛の裏返しであると受け入れるのか。他人に言われることじゃないと気を悪くするだろうか。それとも百も承知で、それでも違う道に進むんだろうか。想像したところで分からないけど、新しいことを始めるのに勇気がいるのは誰だって同じはず。それだけの覚悟を持って、今までとは違う道に進むなんて、素直に格好いいと思った。
「……もったいないて思うほどの男がまた新しいこと始めようとしとるんやろ? 寧ろ楽しみやん」
「なまえはほんま何でもええ風に言うなぁ。一回でも試合観たら気持ち分かるはずや!」
目の前の彼女はいっそ羨ましいわ、と項垂れた。言っても仕方ないことは彼女も理解しているんだろう。それでも言わずに居られない魅力があるというのだから、稲荷崎のアイドルと言われるだけのことはある。
「まぁそんな言うんやったら一回見てみたなるな」
「行こうや! 今週末も練習試合あるて言うてたで!」
「私も部活やから無理やわ」
「そんなぁ……」
ほんまにほんまに二人ともかっこええから!と力説された。彼が引退するまでに一度くらいは機会があるだろうか。
続けてきたことやめて新しい道へ進むのはいつだって不安だ。だけど今まで頑張ってきた事実が消えるわけじゃないし、やる前に諦めることで数十年後に後悔はしたくない。怖がらずに、新しいことを始めてみたいと、そう思った。
◇
高校三年、部活を引退した。幼い頃からずっと続けてきた唯一に、区切りをつけた。出来るとわかっていることをやめて新しい道を選ぶのは勇気がいるけど、不思議ともう怖くはなかった。進路調査票には学びたい学部のある大学名を書き込んだ。正直、今の成績だと相当必死にならないといけない。部活顧問からは今後も続けるつもりならそれなりのところに突っ込めるのに、と言われた。それじゃ意味がないんで、と断るには相応の勇気が必要な成績だったけど、このままズルズルといくのはやめにしたかった。部の後輩の指導もそこそこに、ひたすら勉強に励んだ。
引退が特別早かった方ではないと思う。大会のシーズンは部によって違うから皆バラバラだ。春、夏、秋、少しずつ誰かの夢が終わっていく。残った誰かは、種目も頑張ってきた形もまるで違うのに全部託されたみたいになって、全国へ進む部は学校を挙げて応援する雰囲気になる。
バレー部は県内では常勝だ。だけど春高バレーの本戦は東京だから、甲子園みたいに全校で行くことは出来ない。代わりに、県予選最後の日には学校からバスが出るらしい。クラスの有志で応援に行くことになった。吹奏楽部のコが応援ルールについて事細かに教えてくれた。バレーボールのルールならいざ知らず、ウチ独自の応援ルールまであるとは驚きだ。基本的には応援団に合わせればいいというけど不安が残る。軽い気持ちで行くと言ったのは間違いだっただろうか。
いよいよ明日というところで、休み時間の教室、クラスメイトたちと集合時間を確認していた。
「バレー部の試合、初めて見るわ」
思い出したように呟けば、熱心なバレー部ファンのコから信じられないという顔を向けられる。
「嘘やろ!?」
「現役の間はヨソの部の大会見る機会なんて早々ないやん」
「あー、せやなー。ほな、これも初めてちゃう?」
目の前にずいと出されたのは、それはそれはポップでキュートな応援うちわだった。『あつむ愛してる♡』とか『すなくん今日もするどい!』とか『いぶし銀島』とか結構自由だ。誰がいい?と言われて、これは必ず持たなければならないものなのかと頭を抱える。ゼッタイ持たなアカン!と押し切られ「……クラスメイトやしな」と一人を選び、手に取った。「クラスメイト他にもおるけどな」との揶揄いはなるべく自然にスルーした。男子はあっさり断っていた。
「みんな応援来てくれるん?」
机に突っ伏していたから、聞いているとは思わなかった。斜め後ろ席、治くんが欠伸をしながら身体を伸ばしていた。”みんな”ちゃうけどな、と軽口を叩きながらも「当たり前やん」とか「絶対勝てよ!」とか「負けても骨拾ったるわ」とか好き勝手に返事をしていた。苦笑いで見守っていたのに、治くんと目が合ってしまう。
「みょうじさんも?」
「ん。邪魔ならんよう応援するわ」
「……ソレ振ってくれるん?」
頬杖をついてニヤリと笑う治くんの視線を追うと、私が手に持つ応援うちわ。コートから観覧席では見えなくても、この距離ならはっきりと読めてしまっただろう。『おさむLOVE♡♡』と書いてあった。顔に火が昇った。
「いや、これは……っ!」
「嬉しいわ~。愛ある応援は歓迎やで」
「任せろ」とか「俺も愛いっぱいやで!」とか混ざる面子が揃っていたのだから必死になって否定せず乗っかればよかったのに、頭が回らなかった。
「ちゃうねん! さっき必需品や言うて配られてな!?」
「ええやん、めっちゃがんばれるわ。ちゃんと振ってな。見つけるから」
「恥ずかしいからもう言わんといて……」
家に忘れてしまおうか、との企みは「忘れてもいっぱいあるからダイジョーブやで!」とのフォローにより打ち消された。
春高バレー、兵庫県代表校決定戦、当日。クラスで集まって座席を確保する。応援するだけだっていうのに、心臓がうるさかった。自分が出る大会とはまた別の緊張に襲われる。いざ試合が始まってしまえば、息つく暇もない。当たり前だけど体育の授業とは全然違った。それから選手たちが……宮くんが、教室とは全然違う。
目まぐるしく動く試合展開に圧倒されっぱなしだった。結果はストレート勝ち。大勢の観客と一緒に、歓声を上げた。
試合中は観客を思い出す隙もなかったのだろう。試合終了後、治くんは初めてクラスのかたまりを見つけたらしく、声援に手を振って応えてくれた。目があった気がするのは、盛大な勘違いだ。別に、アイドルじゃなくてクラスメイトなんだから目くらい合ってもおかしくないのに、動揺した。手に持つ応援うちわを小さく振り返した。心臓の高鳴りはしばらくおさまりそうにない。
◇
冬、冬休み、春高。きっと、治くんにとって最後の公式試合になるんだろう。その日ばかりは机じゃなくてテレビにかじりついた。自分の部屋にテレビがあってよかった。どんな結果になっても感極まって泣く自信があった。あの日うっかり持って帰った応援うちわを握りしめて祈った。試合中も試合後も泣いた。
新学期、もう登校する日は多くない。それでも初日の始業式にはクラス全員が揃っていた。バレー部員はどこに行っても囲まれていた。一年からずっと同じクラスで比較的親しい角名くんとは少し話すことができた。治くんにも声をかけたかったけど良い言葉も浮かばずタイミングもなく、午前だけで終わりの一日はあっという間に放課後を迎えた。HRを終えて人が疎らになった教室で他クラスが終わるのを待っていた。
「誰か待っとるん?」
携帯から顔を上げて振り向くと、治くんが教室の扉に手をかけて立っていた。もうとっくに教室を出ていたのに、戻ってきたのは何か忘れ物だろうか。制服姿で、鞄はその手にない。教室に入ってきた宮くんと入れ替わりで、まだ残っていた他のクラスメイトも皆帰っていってしまった。
「二組のコと帰る約束しとって、向こう終わるん待機中」
「あのセンセー、めっちゃハナシ長いよな」
「せやねん。そろそろお腹鳴りそうやわ」
「みょうじさん意外と食い意地張っとるよな」
「治くんに言われたない」
「そらそうや」
軽口に軽口で返すと、宮くんはからからと笑った。コートの中とは全然違う。あのピンと糸を貼ったような治くんを見ることは、もう無いんだろう。もったいない、とは思わずとも、どこか寂しい気持ちはあった。
宮くんは話しながら自分の席に歩いていった。その机の横には見慣れたエナメルが掛けられている。どうやら忘れ物は意外にもソレらしい。
「今日はまだ行くんやね、部活」
「ミーティングだけやけどな。年末でロッカー片付けきらんかったからコレは荷物入れる用。今は空っぽや」
そう言って空っぽのバッグをこちらに向けた。これまでなら忘れるはずもなかっただろうもの。中身の入っていないエナメルを見ると、胸にぽっかり穴が空いたような気がした。
「何か寂しいなぁ」
「……応援してくれとった?」
そんな胸中を見透かすように送られた質問。脈絡なくとも、何のことか分からないはずはない。テレビの向こうにエールを送った、春高。
「……テレビにうちわ振ってもーた」
「そんな気したわ」
急いではいないのか、宮くんはエナメルを持って近くの机に腰掛けた。どうやらもう少し会話に付き合ってくれるらしい。
「結局、生では一回しか観れんかったけど、私も治くんのファンなったわ」
「……ただのファンなん?」
「うーん、熱烈なファンかも? 春高テレビで見とってちょっと泣いてもーたし」
「泣くとこあった?」
「あったあった。……めっちゃカッコよかった」
もう随分と長い間、その背中に勇気を貰ってるよ。そんなことを言えば別にあげた覚えないけどと返されるんだろう。
やめると決めたことを最後までやりきること、その先の新しい挑戦を見据えること。周りにも認められるほど「出来る」と分かっていることを手放して、別の何かを一から始めるのは、すごく勇気が必要だ。だけど怖がる必要なんてなくて、誰より自分自身が楽しみにして立ち向かっていきたい。治くんを見ているとそんな風に考えるようになった。
「俺、バレーやめてもかっこええ予定やから」
「うん? うん」
「楽しみしといてくれるんやろ?」
緩やかに笑う治くんと視線がかち合う。瞬きを繰り返して疑問を訴えても治くんは微笑むばかりで答えをくれない。見つめられることに慣れていなくて、思わず視線を逸らした。すると治くんは何やら脱力して、まぁ覚えとらんよな、と零すように口にした。
「バレーやめた俺も楽しみや、ってみょうじさんが言うたんやで」
「私が? いつ?」
「二年のとき。俺に言うたわけやなくて、誰かと喋っとったと思う。俺がバレーやめるんもったいない〜て言う女子にバレーやめても楽しみな男やん、って返しとったわ」
「私そんなエラそうなこと言うたん!?」
何目線やねん、私。羞恥で顔が熱くなる。治くんがバレーやめるのもったいない、と何人もが口にしていたことは覚えている。だけど、そんな風に言ったどうか、記憶は曖昧だ。
「あの頃はそんな風に言うやつ誰もおらんかったし。おもろいなぁと思って覚えてた」
治くんとは、二年の頃はほとんど接点がなかった。あの頃は自分のことでいっぱいいっぱいで、皆が注目するバレー部にも双子にも特別な興味はなかった。だけど治くんがきっかけで、部活をやめたあとの自分がクリアになった。三年になっても同じクラスで、何度か席が近くなったり、初めてバレー部の試合を観に行ったりして、よく話すようになったと思う。私が意識してしまっているから、だと思っていた。
「別に俺に興味あって言ったんやないってすぐ分かったからちょっとショックやったわ。そっからみょうじさんのこと見るようなってん」
「なに、何のはなし」
「いま教室戻ってきたんも、みょうじさんまだ残っとるて聞いたからやねんけど」
「ちょ、ちょお待って」
思わず両手をかざして制止すると、治くんは「ええけど」と言って黙ってしまった。止めたところで、処理は現実に追いつきそうにない。心の準備ができそうにない。
「これ、何? 何の話しようとしとるん?」
「考えとるままやと思うけど」
意地悪な言い方をする。私が動揺しているのが面白いのか、治くんは楽しそうに笑っている。考えているままの話だというけれど本当にそうだろうか。暇だからってからかっているんじゃないだろうか。もし本当に、これが想像する通りの話ならこっちは寝耳に水だ。だって、もうすぐ卒業だ。登校する期間はあと僅かで、クラスは解散して私たちは皆、別々の道を行く。治くんはバレーをやめる。その道を応援したいと思ってはいたけど、それは私の勝手な思惑で、治くんには届かないところにある想い。だったはずなのに。
「……もう、ええ?」
「あかん。待って、全然あかん」
「早よせな二組終わるやん」
最後まで言わせてや、と治くんが言った矢先、廊下から人の移動する音や声が流れてきた。机に置きっぱなしだった携帯が短く鳴った。待ち人が来てしまう。治くんも気が付いたのか、急かすように私を呼んだ。思わず身体が強張る。視線を泳がせても逃げ場はない。
「みょうじさん」
「……何でしょう」
「ふ、何で敬語やねん」
「緊張するやん!」
「緊張するん俺やと思うけど、まぁええわ。……バレーやめた俺のことも見といてくれる?」
拒否する理由なんて無かった。素直に頷くと、治くんは小さくガッツポーズした。
バレーをする治くんをもっと早く知りたかった、もっと長く見ていたかったと思った。だけど、バレーをしている治くんも、そうじゃない治くんも、全部格好いい。もうすぐ卒業だとか別々の道を行くとか、すべてが些細な話に思えた。
